9/6(土)
10/5にアンサンブルレッスンがあり、ソロを任せた経験者さんや、合奏パートを弾く大人初心者さんが練習をがんばっている。特に1楽章のソロを任せたヒヨさんと、3楽章のソロを任せたリンさんは必死だ。
今日はリンさんがレッスンに来た。リンさんは小学2年生からバイオリンを習い、中学受験の前に新しいバイオリン教本の5巻まで行った。しかし体を不必要に締めながら弾くクセがあり、演奏フォーム(型)もできていない。体をゆるめる必要性やトレーニング方法、バイオリンを弾くときの体の型について、地道に学んでいる。若いため、型については、学ぶと弾きやすくなるようだ。(年齢が高いと、型が弾きやすいと感じられないことも多い。)
今日は左手のてのひらについて説明した。その通りにすると「弾きやすい」「動かしやすい」と言う。それさえ感じることができれば、あとは練習あるのみ。
身体能力にすぐれた生徒は、そんな左手の形に、自動的になる。左手の形は、わりあい自動的に整いやすい部分で、バイオリンを学びに来る生徒の100人に1人は教える必要がない。自動的に整う才能のある人が音大へ進学し、プレイヤーや指導者になるので、99/100人は自動的にならない、ということが分からず教えることになる。小学生のリンさんを指導した先生も、優れたプレイヤーだったのだろう。リンさんの弾き方を見ているとそう感じる。
9/6(土)
ヒサさんは子供を京田辺シュタイナー学校へ通わせていたこともあり、口に入る添加物や農薬には気をつかっていた。経皮毒という言葉も知っていたが、実践はまだだった。ヒサさんのまとっているイソシアネート(企業の宣伝では「マイクロカプセル」とうたわれている)が気になり、そのことについて押しつけがましくないよう口にしていたら、ついに衣類の洗剤を変えてくれた。
レッスンに来られた時、身にまとっている空気感や匂いがまったく違っていたので、変えたのだなと即わかった。体がゆるんでいるので、これまでより背が高く、大きくなったように見える。もう半年その状態が続いている。元の体には戻っていない。
私が新しいフォームを提案したとき、それが弾きやすいと感じられなかったら、経口毒(食品添加物、農薬、家畜の抗生物質)、経皮毒(洗剤、シャンプー、生理ナプキン)、電磁波(スマホ、WiFi、電気自動車、床暖)などを疑ってみるのも方策だ。
体のゆるんだヒサさんには、すごい変化が起こった。生徒さんが弾いている最中、私が、体の部分をちょっと押したり引いたりすることがある。今日ヒサさんの歪みを、私が押して直したら、あれっ!弾きやすいです!と彼は言ったのだ。体の感受性がにぶっていると、そう反応することはなかなかできない。
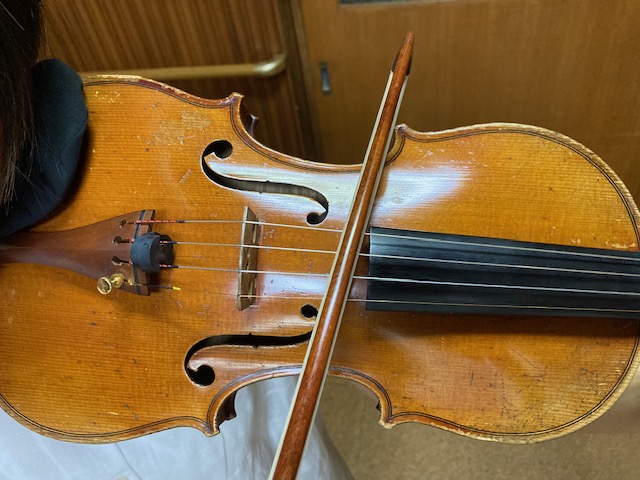
9/13(土)
同じくらいの進度の生徒が、連続したレッスン時間になることは、そうそうない。今日は10/5のアンサンブルレッスンに参加できないテラさんと、同アンサンブルレッスンでビオラパートを弾くことになったオオさんが続けてやってきたので、「春」の三重奏をした。
ヴィヴァルディ「春」のビオラパートの音程に、C線は出てこない。つまりバイオリンで弾けるのだ。ビオラパートは2ndバイオリンパートより大分易しいので、オオさんに「楽やで」と誘いをかけ、私が楽譜をト音記号に書き換えた。
3人で弾いて、オオさんにはビオラパートの面白さ(楽で渋い)が少し伝わったようだ。テラさんも、アンサンブルレッスンに参加できないのに合奏気分が味わえて、嬉しそうにお帰りになった。
9/20(土)
枚方市のくずはから、2ヶ月に一度レッスンを受けにくる生徒さんがおられる。仕事が忙しくて全然弾けなかったんだけど、今日は気分転換しに来た、と今月も来てくれた。1時間、自分のこだわり、知りたいこと、疑問に思うことなどを話してくれ、それに私が答える。私が答えることの根本にあるものは、いつも同じだが、それが彼にとって腑に落ちるよう工夫する。
今日の1時間の最後は、ビブラートの話になったが、丹田から腕や指を動かしているような状態でなければ(自然な)ビブラートはかからない。というところに導くと彼は、今日は来た甲斐があった!と喜んで帰っていった。
9/22(月)
アルプラザ京田辺での十字屋さんのレッスン。骨折で2ヶ月半お休みさせてもらったが、生徒さんたちは怒らず逃げず(?)待ってくれていた。3年目に入ったトミさんは、私が教えてきた家での練習の仕方を心得ていて、基礎的なことをちゃんとこなせている。半年前習い始めたハルさんの、バイオリンを弾くコツは全く衰えていない。
ハルさんは学業が忙しいとの理由で、バイオリンは暫くレンタルを希望し、まだ買っていなかった。ハルさんの優れた身体能力に思わず「バイオリン買おうよ!」と言うと、彼女は顔をパッと明るくして「久しぶりなのに以前と同じように弾けてびっくりした」「買います!」と。これからの二人三脚が楽しみだ。

9/24(水)
バイオリンの習い始めは誰でもそうだが、知っている曲が教本に出てくるとやる気が増す。大人の初心者さんでも子供でも同じだ。ところが最近の子供たちは童謡・唱歌をあまり知らない。
私がほぼ全員の生徒に使ってもらう「やさしいヴァイオリン曲集<上>」の1曲目「春の小川」も、知ってる子より知らない子が増えてきた。後ろに控えている保護者さんが、ええ~!あんた知らないの?と驚くが、そうなのだ。「夕焼け小焼け」も「お正月」も「雪やこんこん」も。
知らない曲が多めのコユちゃんは「春の小川」に全く興味を示さず。しかし何か月かレッスンをして、彼女のやる気を増す法則を見いだした。先に歌うのだ。楽譜を読ませて弾いてもらおうとしてもサッパリなのに、私が歌って耳から入れると、急速に彼女の中へ入ってゆく。
「春の小川」は、歌詞を書きこんで先生が歌った(保護者さんにもおうちで歌ってもらえるようメールした)一週間後、見事な演奏を披露してくれた。ええーあんさん、先生が何回レッスンしても全く興味示さんかったやん。今までの苦労は何だった?
次の課題は「お正月」にした。先生がバイオリンを弾いても反応せず。しかし歌詞を書き込んで歌うと、少し眼が輝きだしたような・・気がする。(コユちゃんは元々物静かな子であまり喋らない。から反応がよくわからない。)
保護者さんに「お正月」を歌ってくれるようメールしたら、後日お返事がきた。デュエットの課題曲「ハイホー」の歌詞を教えて!と言われたそう。ハイホーに歌詞なんてあったかいな。ハイホー!ハイホー!のとこしか知らんぞ。調べたら歌詞あった。
コユちゃん曰く「小人さんが踊るからそんな風に弾くよって教えてもらった!」と言ったそう。歌の曲だとは言ってないが。「小人が踊る」にも反応するんや、コユちゃんは。
このように情報を得て、レッスンの精度を上げていくのであった。
9/25(水)
私のレッスンでは時々バイオリンを置いて、体の使い方(だけ)のレッスンをする。椅子に座る、立つ。竹刀を振る。重い引戸を開ける。重い椅子を持ち上げる。お茶碗を持つ。生徒さんの弱点に合わせてチョイスする。いずれもアレクサンダーテクニークの基本動作に、バイオリン演奏時の体の使い方をふまえたアレンジをして、レッスンしている。
9/6で述べたヒサさんには、引戸の開け閉めを特訓?し、日常生活に生かしてもらっている。彼が驚くほど変わったのは前述のとおり。
今日はイシさんに引戸の開け閉め、椅子を持ちあげる動作をやってもらった。彼女は仕事で毎日のように、何十脚もの椅子を並べたり片付けたりするそうだ。仕事中にトレーニングできると、嬉々として帰られた。

9/27(土)
バイオリンを習い始めて2年目、5年生のヒカちゃんが、京田辺音楽家協会 主催の「アンサンブル体験会」に出たいと言った。課題曲を見るとザイツやモーツアルトの協奏曲。
「スズキの4巻から10巻の曲なのよ」と伝えて、一番易しいザイツ協奏曲の1ページ目を渡してみた。出だしのワンフレーズだけ教え、「弾いてみたければ続きをやってらっしゃい」と言うと、今日 半ページほど進んできた。
ヒカちゃんは弓がまっすぐに引けない。弓をギュッと握りしめているから弧を描いてしまう。「最初の3つの音は、弓がまっすぐ進まないと弾けないのよ」。 次回も進んでくるだろうか。
10/3(金)
次の日曜日は、8カ月に1度のアンサンブルレッスン。チェロ初心者のナオさんが、足を骨折したことを思い出した。そんなところまで先生に似なくていいのに。チェロトップの松原さんに連絡して、当日の朝迎えに行ってもらえるよう手配。私が行ければいいのだが、会場の設営と、カナさんの個人レッスンがある。
10/5(日)
アンサンブルレッスンの日。みなの集合前にカナさんのユーモレスクのピアノ合わせがある。大人のカナさんは初心者だけれど、体の使い方がかなりよい。しかし今日は緊張して普段はとちらないところで音が出ない。観察していると、左指が行くべきところが分からないようだ。
この現象は頭で歌えていないときに起きる。合わせを止めて、「バイオリンを弾くという行為の前に、脳みそで曲を再現して」「弓を動かそうとか、左指は1だ2だとか、考えない」と伝えると、すらすら弾き出した。いつもより硬かったが上手だった。集まり始めていたアンサンブルの生徒たちからも拍手が。
さて、松原さんがナオさんのチェロをしょって来てくれたが、彼女も腰を痛めてサポーターをしているとのこと。松原さんは私の骨折を知らなくて、私から「おくれてる」と言われ、生徒たちから「せんせーのブログに書いてるよ」と言われていた。
帰りのチェロ運搬は、ピアノの momo先生 にお願いした。
打ち上げ?のランチ会の片隅で、momo先生と11月の仕事の打合せをする。奈良の生長の家「自然の恵みフェスタ」というイベントで、毎年ピアノと歌のコンサートをしているが、バイオリンも加わって欲しいそうだ。こうしたイベントではポピュラー曲が中心のプログラムが喜ばれる。
私が請け負い人のばあい、抵抗して純クラシック曲も1つ2つ入れるのだが、船頭が多いと山に登ってしまう。候補曲だけ2人で決め、そこから選ぶのは一任する。momo先生は、練習したてだからという理由(^^;) でユーモレスクがいいと言う。ほか情熱大陸、日本の歌、愛の挨拶、見上げてごらん、君をのせて、花は咲く、などが候補にあがる。
会場は響かないところだそうだ。イベントにありがち。シャープ4つの愛の挨拶、フラット6つの君をのせて などが心配だ。

10/8(水)
メイちゃんの演奏フォームが俄然よくなっている。理由は明白で、3/4の分数バイオリンを買ってもらえることになったからだ。「弓が端まで使えてないのに、次のサイズに上がれるかな?」「その左指では、一段階大きくなったバイオリンの指板を抑えるのはムリ」と、3/4へ向けた課題を提示している。
身長的にはまだ1/2の高さなのだが、春から7年生(京田辺シュタイナー学校)になるので、その前に少々背伸びをさせてみることにした。同級生で身長も同じくらいのスイちゃんにも、冬休みくらいに3/4へサイズアップしましょう、と提案。
うちの教室では、分数バイオリン や 大人初心者バイオリン は、大阪府茨木市のアマービレ楽器で買うことをお勧めしている。理由は以下の通り。
①中古が多い。バイオリンは木工品だから、中古のほうが軽くなり、響きがよいことが多い。
②安い。コストパフォーマンスがよい。
③選択肢が多い。サイズと値段を指定しても、複数台から選べる。一般的な楽器店では、全サイズ店頭にあることも少なければ、同サイズで同価格帯の楽器は置いていない。
④品質に厳しすぎない。(品質に厳しい=販売価格が高くなる) けれど購入後の使いにくさ(顎当ての高さなど)にも、誠実に対応してくれる。
⑤下取り価格が高い
アマービレで買うときの注意点もある。それはお配りする資料をよく読んで、先生のアドバイスをよく聞いてください。
生徒の(保護者さんの)ニーズを見て、大阪梅田のクロサワバイオリンを勧めることもある。同時に肩当HAYATEも買える。(店頭で買うと後々のフォローも受けやすい。) 京田辺市からは電車でも車でも近い。品質にはかなり厳しい。
バイオリン・ビオラは買ったあとにトラブルが起きやすい商品だ。だから、後で困ったときに対応してもらえる、そのとき余計なお金がかからない、ということがお店選びで大事になる。「そのとき安いこと」より「あとあとの安心感」が大事だと、自分自身の体験や生徒さんたちを見ていて思う。

10/9(木)
習い始めて数か月の3年生ハルマくん。当初体がぐねぐねしていたのに、左手首が曲がっていたのに、真っすぐになってきた。身長も伸びてきて、体格がしっかりしてきた気がする。1/2を持たせて丁度よかった。音程も音色もよい。
6年生のハルマくん。彼はまだ1/2の分数バイオリンで、身長が伸びないかと先生はいつも期待をもって観察しているのだが、伸びない。男子は、最終完成形が女子より大きくなるので、3/4や4/4へのサイズアップのタイミングは女子より遅らせる。昔、中学校にあがってから 1/2→3/4へサイズアップした男子がいたが、6年生のハルマくんもそうなりそうだ。
子供の男子はほかに4年生のヒロトくんがいる。もともと大きくて最近ぐんぐん背も伸びてきたが、前の冬に3/4へサイズアップ済みだ。
10/12(日)
神戸フェニックスフィルの練習日。骨折してから初めて兵庫県へ行った。今日はビオラが1人しかいないとのことで、10日ほどハ音記号の楽譜を頭に叩き込んで、ビオラを担いで出かけた。
本番のパンフレットには「トレーナー中川恵」と紹介されているが、このアマオケにおける私の役割は不明瞭だ。団の中核者が、トレーナーという立場の者(私)の使い方を分かっていない。けれど自分からあれこれ言いたくないので、黙っている。長らくストレスを感じていたが、友人に「それは恵さんに起因しない」と言われて少し気が楽になった。
ビオラトップに「ここはダウンが良い」と言うと、仰せの通りにします、という反応だ。「ここはダウンが良い」と言われたら、何故そうなのかを考えてほしい。トレーナーに「ダウン」と言われても、自分に違う考えがあれば、そちらを採用してほしい。私は助言した相手が私の助言を受け入れなくても、なにも言わない。
同様に、トレーナーが自分が付けたボーイングと逆を弾いていたら、それは何故なのか考えてほしい。けれど同じ個所を何回逆に弾いても、無反応だ。
トレーナーは迷っていることもあれば、ただミスってる場合もある。高度すぎる要求かもしれないが、それも見分けてほしい。(自分のミスは棚に上げる。) 迷っている場合は、同じ個所を弾いても都度違うボーイングになる。ミスってる場合は、2回目からは異なるボーイングになる。アンサンブルにはそういう察知力もいる。
レッスンでも、できるだけ生徒自身に気づいてもらえるよう振舞う。その方が、人を成長させるやり方として本質的だからだ。私自身もあれこれ指図されるのは嫌いだ。自分で気づけるまで待ってほしい。

10/17(金)
京田辺教室に不定期で訪れるようになったムラさん。ヤマハ音楽教室で5年レッスンを受け、ポジションに入ったところだったそうな。
耳が良すぎて、調号(シャープやフラット)と、指板に左指を置く位置の関係を理解しないまま、曲を弾いていたことが判明。次のレッスンから特製のプリントをやってもらうことになった。このプリントをすると、左指を置く位置の規則性が、視覚的にわかる。
ムラさんは前々回のアンサンブルレッスン、パッフェルベルのカノンやアンダンテ・フェスティーヴォをやった回に参加して、2ndバイオリンパートも弾いている。音楽力の高い人だ。
アンサンブルは人生初だったのか、自分の音が聴こえない!状態にショックを受けたそう。正しい音程が弾けているのか分からない、ちょっとズラして出してみたら、自分の音が聴こえた。そこで「自分の音が聴こえないときは、音程が合っている」と分かったそうだ。
10/20(月)
月4回レッスンにくる真面目なダイさん。今はジブリ曲集をやっている。生徒の多くが知っている曲を弾きたがる、知っている曲の方がやる気が出るようだ。京都三条の十字屋へ行くといつも、生徒に合った曲集や教本が出ていないかチェックする。
昔からよく使っているのは全音楽譜出版社の「やさしいヴァイオリン曲集」上下巻。最近よく使うのが、YAMAHAのジブリ作品集のグローバル版だ。初級編、初級~中級編、中級編と3グレードあり、薄くて安いため初心者さんのレッスンに使いやすい。
ダイさんは初級編の「もののけ姫」をやっているが、中盤にV-V(アップ休符アップ)の箇所が出てきた。Π-Π(ダウン休符ダウン)は初心者向けの楽譜でもよく出てくるけど、VVは珍しい。教えていないのにダイさんは自然にそれらしく運弓した。これまでのレッスンで右腕・右指を細かく指摘され、努力してきたからと思われる。自己流の弾き方をしているアマオケ奏者にはできない動かし方だ。
ダイさんはビブラートが出来ることを目指している。体幹、左腕のあり方、左指の使い方がよければ、ビブラートは自然とできるようになる。というのが私の教え方だ。生徒たちがそれを証明している。
10/20(月)
イシさんに、洗剤を変えると身体感覚が良くなって、バイオリンが弾きやすくなる実例を話した。そして経費毒についてまとめたブログ記事を読んで、興味のあること出来そうなことをピックアップしてくるよう宿題を出した。
大人の初心者イシさんは熱心に練習をするが、なかなか成果が表れなかった。バイオリンを弾くときの肩や肘の位置、弦に対する弓の角度、左手首の角度など。様々な説明や手法で繰りかえしても、思ったほど前進しない。
立ったり座ったり、椅子の運び方、ドアの開け方。体の使い方を改善しようとしても良くならない。
イシさんに一番必要なのは、バイオリンの弾き方ではなく、日常生活における体の使い方でもない。長いこと機会を伺っていたが頃合いだと思った。

10/22(水)
今日最初に来られたテラさんには、沢山歩くことでバイオリンが上達する話をした。彼女も合成洗剤を使っている(マイクロカプセルが漂っている)が、体の使い方を変えていくことで、バイオリンの弾き方にも変化が見られる。習い始めのころは弓の真ん中しか使えなかったが、今は端から端まで使えている。
最近の子供たちは本当に歩かない。「玉水駅前で車から降ろしてもらい、走ってくるように」と言ってもやらない。3000円払ってレッスンを受けるより、30分 野山を駆け回っている方がバイオリンはうまくなると思う。
次に来られたヤマさん。健康診断で要精密検査となり、アレルギー体質、糖尿病予備軍、腎臓が弱っていることなどが分かったと言う。アレルゲン物質を多数指摘され、腎臓が弱っている原因はロキソニンやステロイド軟膏だと言われ、ショックを受けている様子。
アレルギーは免疫の働きを適切に抑制できないことからくる病気だが、「免疫の働きを適切に抑制する」仕事は、自分自身の体(DNA)だけでなく、腸内細菌も担っている。だから自分のDNA能力は変えられなくても、腸内細菌を優秀?にできれば症状を改善できる。(腸内細菌を優秀にする=数を増やす+多種多様にする方法は割愛する。自力でいくらでも調べられる。)
それより、現代社会の便利なものは たいてい腸内細菌を劣化させる。そうでなければ こんなに自己免疫疾患が増えるわけがない。そうしたものを日常生活から引き算していくほうが、取組としてより本質的・根源的だ。
ヤマさんは12年通ってくれている生徒で、日常生活を変えることでバイオリンが弾きやすくなる体験をしてきた。食べ物をどうすべきか、という話に、今日はいつもより熱心に耳を傾けてくれた。
10/26(日)
サラちゃんは普段から生気のない顔でよろよろしている。バイオリンを体の前に抱えてペグを回す力もない。そんなに固いのかな?と思い私が回すと、なんなく動く。ビンの蓋なども開けられないのだろう。
このところ本人に少しづつ「体が、バイオリンを弾く土台である」「バイオリンをさらう前に、体力や筋力が必要だ」という話をしていたのだが、今日たまたま親娘でいるところに出くわした。たまたま保護者さんが「これこれこんなことがあって」「筋力のなさが心配」とおっしゃった。しめた!
「まず歩きましょう」「ここから家まで10分くらいですよね。手始めに今日は歩いて帰りましょうよ」と提案してみた。別れて暫くしてから振りかえると、2人は、お友達の保護者さんの車に乗り込んでいた。

10/29(水)
2月の発表会の会場にと考えている、奈良の音声館(おんじょうかん)へ行った。3か月前抽選で、反響板&袖幕のステージがあって、最大90席で、値段が安い。備品系の値段は変わらないが、ホール代(スタッフ人件費 含む)がよそとゼロ1桁違う。響きがイマヒトツなのが残念だが、ほかの条件がよいので目をつぶる。
今日は設備について細かく確認し、費用を見積もってもらった。ホール代が6000円、ピアノ(スタインウェイ)代が16000円。ピアノのmomo先生には素晴らしい伴奏を期待しよう。
終わってから打ち上げ会場をさがしてカフェをはしご。紅茶を3杯飲んだ。
11/4(火)
宇治フィルのタナさんが久しぶりにいらした。頻繁にではないが、弦楽四重奏や三重奏を見てもらいに宇治フィルの面々と来たり、個人レッスンに来たりする。理解度も身体感覚も高いので、じわじわと良くなっている。
11/14(金)
姿勢に課題のある中学生のアイちゃん。頭部がいつも前方にずり落ちている。様々な声かけにより改善することもあるのだが、長持ちしない。
今日はふと、先日テレビで観たベートーベンの協奏曲で、ソリストが、顎当てから頭部を完全に浮かせて弾いていたことを思い出した。試しに「顎当てから顎を浮かせて弾いてみて」と言ったら、弾きやすいようだ。
顎当てが低すぎると気づいたので、応急処置で、手持ちのコルクを挟んで高くした。その方が姿勢がだんぜん落ち着いた。顎当ては古くて少し腐食しているようだったので、バイオリン工房へ行って高さのある顎当てに交換してはどうか?と提案。
11/15(土)
ハバさんの顎当てを、金具がU字型のものから、ヒル型へ変えてみた。人体とバイオリンの接点(首元)がなかなか安定しないのは、顎当て金具のせいではないか?という話になったのだ。丁度 井手町教室に、お皿のタイプが全く一緒で、金具だけ違うものがあり、取り替えてみたらとても弾きやすそうだった。その場でお買い上げとなった。ストック品は頻繁に役立つものではないが仕入れといて良かった。
顎当てをバイオリン本体にとめている金具は、左右の脚がつながったU字型のものが多い。しかし中には(フルサイズの1割くらいだろうか)、左右が独立した柱のようになっているタイプがある。ヒル型という。
深山直久先生は「ヒル型だと鎖骨の端に金具が当たらず痛くない(から良い)」と言っていたが、ヒル型は2本の金具の下端がゴツく、それが当たっている箇所が痛いのでは、と思っていた。

11/19(水)
井手町教室は玄関ホールが待合室になっているが、夏は暑く、冬は寒い。かと言って暖房器具を置いといても、器具があったまるころには自分の番になって先生に呼ばれる。付けっ放すにしても、玄関・廊下・洗面所とひとつの空間になっていて効率が悪く、電気代が恐ろしい。
しかし今年は新兵器が登場した。カフェ志木さんから借りた床に置くセラミックヒーター。足をのせて温もってください。

