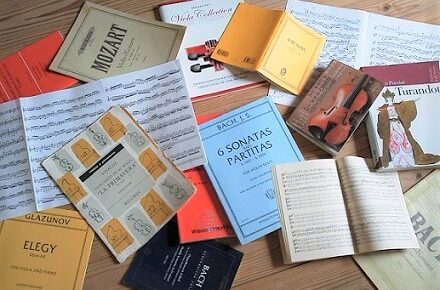01
体が動けば、バイオリンは弾ける
バイオリン特有の体の動かし方を覚えることで、バイオリンは弾けるようになります。日常生活にはない特殊な動きなので、独学は難しく、客観的な指導者の目線が必要です。
体の動かし方を教わっても、その通りに動かせるかは別問題です。ここに挫折するかしないかの分かれ道があります。アレクサンダーテクニークをはじめ様々な身体メソッドを学んだ経験を活かし、動かせる体を作っていきます。子供たちは素直な姿勢に育ち、大人は体が楽になります。

02
足し算と引き算
バイオリンを弾く動作ができるようになるには、2つの要素が必要です。
①必要な動きができるようにする(足し算)
②不要な動きをしないようにする(引き算)
必要のない筋肉に力が入っていたら、それが邪魔をして、動かしたい筋肉が使えません。習い始める年齢が上がるほど上達しにくいと言われるのは、引き算せねばならぬものが増えてくるからです。
現代社会では、若年層ほど幼少期に体を動かしていないため、子供時代にしっかり外遊びをしたシニアの生徒さんが有利なこともあります。

03
練習は量より質
変な姿勢で練習すると、変な弾き方が身につきます。質の悪い練習は、ヘタになるためにやっているようなもの。練習のやり方によっては体を痛めることもあります。
どの本のどの頁まで進んだかではなく、「何ができるようになったか」が大事です。しっかり集中して質の良い練習をすれば、だらだら長く練習するより上手になります。
04
家での練習、日常生活の過ごし方が大切
レッスンとレッスンのあいだの日々の過ごし方が大切です。教わったことを家での復習で身につければ、次のレッスンでは新しいことが学べます。
また1日30分練習したとしても、24時間のたった2%です。98%の時間の過ごし方が大切。日常生活における体の使い方を見直すことで、バイオリンが弾きやすくなります。
05
基礎が大事
「基礎」とはバイオリンが弾ける体作りのこと。エチュードやスケールの教材を1頁ずつ進んでいくことが「基礎」練習ではありません。私の教室では耳コピーのスケールで、それぞれの生徒に必要な課題を出します。
目的別スケール練習 <左手編>
07
あきらめない
上手になりたいという意志を持ってお越しになる限り、その生徒さんを上手にすることを諦めません。 「大人は上手にならない」と言われたバイオリンの先生もおられるそうですが、その考え方には組しません。
08
しばらない
レッスンに来るか来ないかは、生徒が決めることです。合同レッスンや発表会への参加も、なんの曲を弾くかも、生徒さんが決めます。先生のなってもらいたい姿を生徒たちに押しつけないよう気をつけています。